弊所で開催している自治体職員向けの研究会「地域経営部会」では、プログラムの一部として「地域研究会」を開催しています。今年度、この地域研究会はマネ友と呼ばれている過年度生が中心となり企画・運営しています。参加者はマネ友を始め、部会に集っている現役生もいれば、部会に参加したことのない方も集っていることもあります。
本日は茨城県内で実施されたイバ研(茨城地域研究会)の模様をご紹介します。因みにこのレポートを書いてくださったのも、企画しているマネ友のお一人です。

日時:2025年7月31日(木)
10:00-15:30
場所:東海村産業情報プラザ
主催:一社)Maniken
茨城地域研究会
参加者:8自治体 27名
(東海村,高萩市,ひたちなか市,笠間市,石岡市,龍ケ崎市,常総市,古河市)

AM
レク①「これからの地域経営に必要なこととは」鬼澤慎人
ダイアログ①②私たちの仕事と地域とのつながりを考えてみよう
―昼休憩-
PM
レク②「一歩踏み出すとは」鬼澤慎人
ダイアログ③④私たちが一歩踏み出すために必要なことは何か
クロージング(振り返り、集合写真、アンケート)
【研究会の様子・感想】
 まず,鬼澤さんから今の地域に必要なことは,まず行政が経営の質を高めることだとレクを受けました。そもそも経営は,目的・想い・夢を持ち,構想や道筋を立てて,実行して成果を出すことであり,市町村行政は国の出した構想・道筋を実行管理しているだけだった。いま,管理から経営へ組織変革が求められており,それが地域を経営することにつながっていく。
まず,鬼澤さんから今の地域に必要なことは,まず行政が経営の質を高めることだとレクを受けました。そもそも経営は,目的・想い・夢を持ち,構想や道筋を立てて,実行して成果を出すことであり,市町村行政は国の出した構想・道筋を実行管理しているだけだった。いま,管理から経営へ組織変革が求められており,それが地域を経営することにつながっていく。
これを受けて,地域と我々市町村職員の仕事の関連性をダイアログしました。
「職員は地域からだれでも同じと思われているかもしれない」「地域のために働く人」「地域の課題を調整・解決する人」など自分たちの立ち位置を確認しあい,私たちは「地域」を見て仕事に向き合えているかという自問自答と対話が展開されました。

 2~3年で異動が繰り返され,地域と腰を据えて協同できないはがゆさや柔軟性や職員のパーソナリティを発揮できない組織的な課題についても話があがりました。 また,いつの間にか「地域」ではなく「組織や上司,首長」を見て仕事をしていたことに気づかされる場面もあり,本来我々が地域のありたい姿をどう描き,どこを向いて仕事をし,行動していきたいのかモヤモヤし,考える時間がとれたと思います。
2~3年で異動が繰り返され,地域と腰を据えて協同できないはがゆさや柔軟性や職員のパーソナリティを発揮できない組織的な課題についても話があがりました。 また,いつの間にか「地域」ではなく「組織や上司,首長」を見て仕事をしていたことに気づかされる場面もあり,本来我々が地域のありたい姿をどう描き,どこを向いて仕事をし,行動していきたいのかモヤモヤし,考える時間がとれたと思います。
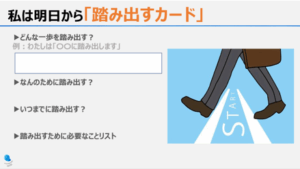 地域と自分の仕事について考えた後,午後のテーマは「一歩踏み出す」。
地域と自分の仕事について考えた後,午後のテーマは「一歩踏み出す」。
踏み出せない要因について,考えて対話してみると「反対意見を言われそう」「時間がない」「人にどう思われるか気になる」など自分の中にある内的要因と,「同調圧力」「前例ありきの慣習」「挑戦を前提としていない人事システム」など組織の仕組や風土に関する外的要因があげられました。
そこで,踏み出すためには何が必要か?を対話してもらった後で,それぞれ一人ひとりが「踏み出すカード」を書き,踏み出す決意をグループ内で宣言してもらいました。

今回,地域経営部会の茨城版としてイバ研(茨城地域研究会)を立ち上げ,県内有志で今回の研究会を開催しました。また,初の試みとして,各自治体へオンサイトでの参加を呼びかけ,業務・職専免扱いなどで参加いただけました。「刺激になった」「自分の殻を破りたい」などいい機会であったという声も多数いただき,開催してよかったと感じています。今回の内容は,知識や技術よりも大事な「主体性」「協同性」を考えていくものでしたが,参加者一人ひとりが自分は微力かもしれないが無力でないことを認識し,一歩踏み出す後押しに少しでもなれていたらいいなと思います。
次回のイバ研は,12月頃を予定しています。自分自身を振り返る場,仲間と語り合う場となるよう,事務局で企画していきたいと考えています。
□イバ研事務局・茨城県市町村職員有志一同
